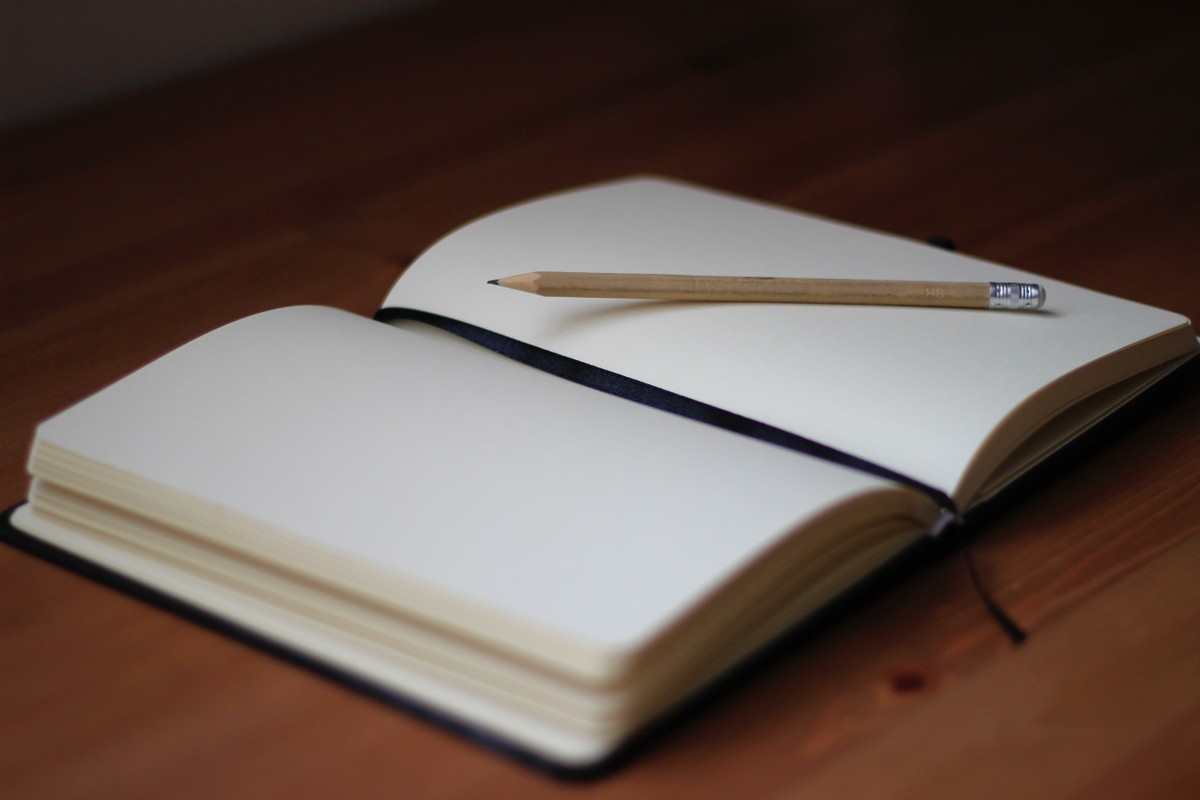
今日はピッグ・ラテンを紹介します。英語の言葉遊びのひとつです。主に子どももペットも分からないようにするゲームなんです。簡単なルールは一つだけあります。単語の始まりは子音があれば、最後に移動され、ayを付けます。例えば、pig->igpay, latin->atinlay, journaly->ournalyjay。
想像の文法もあります。Ix-nayは禁じるという意味のnixを基づきます。英語ではnix on the talkingと言いませんが、ピッグ・ラテンではix-nay on the alking-tayと言うことがあるんです。ちょっと変ですよね?
なぜピッグ・ラテンはピッグ・ラテンと呼ばれるか今まで考えることがないです。私の英語を慣れた耳には少しラテン語らしいですかな。豚は?わからないです。Wikipediaさんに救われません。
モンスターズ・インクという映画にこのゲームのことを教われました。観たときは小さい頃だから、話し合われたことがわからなかったです。しかし、事情がわかりました。本物の言語学習にそっくりだと思います。時々、新しい単語も、文法も聞いたところで、素早く事情を読んで分かるようになる仕方がないです。
しりとりが知っていますが、日本語での他の言葉遊びはあるはずですね。教えてください!
3
俳句や短歌が言葉遊びの類いに入るなら、俳句や短歌もそうだと思いますが、子供が遊べるような言葉遊び、しりとり以外に思い浮かばないです。Amieさんの日記を読んで全く関係ないけど、ピジョン英語を思い出しました。
私はもともと俳句を作るのが趣味だったんですが、回文もかなり作りました。自分が作った回文のなかで我ながらすごい、と思ったのは、
です。1は、日本の皇室に嫁いだふたりの女性の名前を使っているので少し分かりにくいかもしれません。
俳句サークルに属していた頃、そのサークルで編み出したグループで一文字ずつ順番に決めていって俳句を作るという遊びでNHKの俳句番組に出演したことがあります。
英語でも回文がありますよ。多分、日本語のほうが作りやすいです。有名な例は
です。あきこさんの回文を読むときに、辞書検索しがちでした草
日本語はリズムとしてはモーラ言語だし文法的には語順がわりと自由なので回文はとても作りやすいです。
「たほいや」というゲームもあったなあ、と思い出していたのですが、これは英語圏でのゲームの Fictionary のほうが先にあったようです。
Amieさんの紹介してくださった「ピッグ・ラテン」に似ているのは「はさみことば」だと思います。しかしこれも英語にも似た遊びというか、ルールがあるようです。
私の友人の子どもたちが実際にこのはさみことばの一種を使ってました。たとえば「かきくけこ」をはさんで「ありがとう」を言うと「あかりきがくとけうこ」となるんです。私たち大人には何をしゃべっているのかさっぱり分からなかったです。